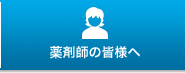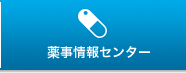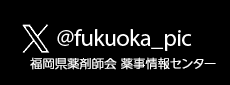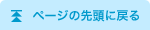質疑応答
質疑・応答をご覧になる方へ

福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。
回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。
県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。
質疑・応答検索
相談内容をクリックすると回答内容がご覧になれます。
※相談内容を検索する際に、検索語に英数字が含まれる場合は、半角と全角の両方での検索をお試しください。
| 血圧測定法の聴診法で確認できる「コロトコフ音」は、なぜ発生するのか?(その他)
検査値・検査方法 |
|
| 年月 | 2016年2月 |
聴診法は、1905年にロシアの軍医ニコライ・コロトコフにより提案された非侵襲的血圧測定法である。上腕に装着したカフ(マンシェット)で動脈を圧迫して一旦血流を止め、その後徐々に圧力を低下させる過程において血管から生じる音「コロトコフ音」の発生と消失を確認することにより測定する。コロトコフ音は、血管が開く瞬間、血管内に生じる急峻な圧力波によって発生する。つまり、血流の渦による血管壁の振動と、脈波による血管壁への衝撃によって発生する。コロトコフ音はカフ圧の変化に伴って5段階に変化する。
|
第1相:音の出現 |
カフで圧迫されて閉塞していた血管が開き、短時間血流が再開して末梢の血液の溜まりにぶつかり、明瞭な叩打音(トントン、タップ音)が聞こえる。血流量は少ないので、乱流が起こるほどの流量はなく雑音は生じない。この時の血圧が収縮期血圧(最高血圧)。 |
|---|---|
|
第2相 |
血流面積が広く、時間が長くなるため逆に叩打音は小さくなる。非圧迫部に流れ込む流量が多くなるため、乱流による雑音(ザーザー)が混じる。 |
|
第3相 |
開口面積が更に大きくなり、非圧迫部との違いがなくなるため乱流が起こりにくくなり雑音は消失する。非圧迫部の溜まりに血流がぶつかる鈍い叩打音(ドンドン)のみが聞こえる。 |
|
第4相 |
血液の流量が増え、非圧迫部の血液滞留時間が短くなり、叩打音が急速に小さくなる。 |
|
第5相:音の消失 |
圧迫部と非圧迫部の血流の流速差がなくなり叩打音は消失する。この時の血圧が拡張期血圧(最低血圧)。 |