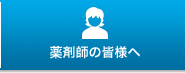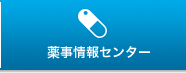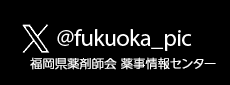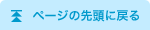質疑応答
質疑・応答をご覧になる方へ

福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。
回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。
県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。
質疑・応答検索
相談内容をクリックすると回答内容がご覧になれます。
※相談内容を検索する際に、検索語に英数字が含まれる場合は、半角と全角の両方での検索をお試しください。
| 上部消化管透視検査でバリウム製剤を使用した後の下剤投与は必須か?(薬局)
副作用、中毒、妊婦・授乳婦 |
|
| 年月 | 2017年3月 |
検査後に消化管内にバリウムが停留することにより、まれではあるが消化管穿孔等が報告されている。消化管穿孔は致死率も高く、救命できても人工肛門の造設が必要なことが多くQOLを低下させるため、排便コントロールによるバリウム排泄が重要であり、下剤の内服や十分な水分摂取が必要となる。下剤の投与法は各施設によって異なるが、大腸刺激性下剤のセンノシド(プルゼニド等)の検査後の投与や、バリウム製剤のコップの中にピコスルファートナトリウム(ラキソベロン等)1mLを予め混入しておく方法が一般的である。通常の処置でバリウム排泄が不十分な場合は、腸管内圧を上昇させるような強力な下剤や浣腸は避け、50%ラクツロースを1回5~10mL、1日2~3回、連日投与の有用性が報告されている。また、バリウム製剤にポリカルボフィルカルシウム(コロネル、ポリフル等)を混ぜることでバリウムの停留が予防できるとの報告もある。