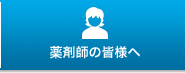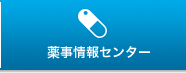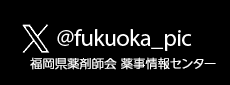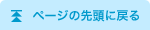質疑応答
質疑・応答をご覧になる方へ

福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。
回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。
県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。
質疑・応答検索
相談内容をクリックすると回答内容がご覧になれます。
※相談内容を検索する際に、検索語に英数字が含まれる場合は、半角と全角の両方での検索をお試しください。
| マドパー配合錠(レボドパ・ベンセラジド配合錠)からメネシット配合錠(レボドパ・カルビドパ配合錠)へ変更する時の注意は?(薬局)
薬効・薬理、体内動態 |
|
| 年月 | 2017年9月 |
レボドパの末梢での代謝を抑制するために脱炭酸酵素阻害薬(ベンセラジド、カルビドパ)が配合されている。臨床現場では、同じレボドパ量であれば両者は同等に扱われているが、健康成人男性において、同じレボドパ量の各配合錠を服用した場合、血漿中レボドパのCmaxやAUCはベンセラジド配合錠の方が有意に高値を示した報告がある(Tmaxは有意差なし)。また、パーキンソン病患者において、同じレボドパ量で、ベンセラジド配合錠からカルビドパ配合錠へ変更した場合は安静時振戦等の運動症状が悪化し、カルビドパ配合錠からベンセラジド配合錠へ変更した場合は副作用が出現した報告がある。従って、配合剤の違いによるレボドパの血中濃度への影響が示唆され、同じレボドパ量でもバイオアベイラビリティが異なることが予想されるため、変更時は用量調節や症状悪化等の観察が必要である。