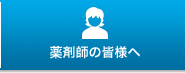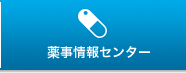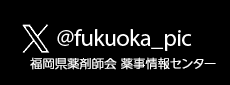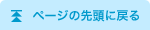質疑応答
質疑・応答をご覧になる方へ

福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。
回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。
県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。
質疑・応答検索
相談内容をクリックすると回答内容がご覧になれます。
※相談内容を検索する際に、検索語に英数字が含まれる場合は、半角と全角の両方での検索をお試しください。
| 臨床検査値のAPTTとは何か?延長を示す場合は?(一般)
検査値・検査方法 |
|
| 年月 | 2014年5月 |
APTT(Activated Partial Thromboplastin Time:活性化部分トロンボプラスチン時間)は、内因系凝固活性の指標で、外因系凝固の指標であるPT(プロトロンビン時間)とともに出血性素因のスクリーニングに用いられ、通常、基準値は27~40秒である。クエン酸加血漿にAPTT試薬(リン脂質と陰性荷電体)を添加して一定時間加温後、塩化カルシウム液を加えフィブリンが形成されるまでの時間を測定する。この凝固過程には、プレカリクレイン、高分子キニノゲン、血液凝固第Ⅻ、Ⅺ、Ⅸ、Ⅷ、Ⅹ、Ⅴ、Ⅱ(プロトロンビン)、Ⅰ(フィブリノゲン)因子が関与する。
ヘパリンはアンチトロンビンⅢを介して凝固第Ⅱa因子を阻止することでAPTTを延長するので、ヘパリン投与のモニターに用いられる(基準値の2倍以内)。
(延長を示す場合)関与する血液凝固因子の減少、機能低下および抑制物質の存在を反映する。
血友病A・B、肝障害、von Willebrand 病、ビタミンK欠乏、播種性血管内凝固症候群(DIC)、薬剤投与(ヘパリン、ワルファリン、抗トロンビン薬)等。