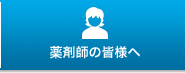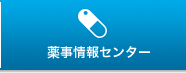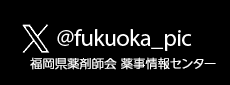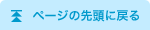質疑応答
質疑・応答をご覧になる方へ

福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。
回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。
県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。
質疑・応答検索
相談内容をクリックすると回答内容がご覧になれます。
※相談内容を検索する際に、検索語に英数字が含まれる場合は、半角と全角の両方での検索をお試しください。
| 悪性症候群の発現機序は?(薬局)
副作用、中毒、妊婦・授乳婦 |
|
| 年月 | 2013年4月 |
悪性症候群は、主に精神神経用薬服用下での高熱、意識障害、筋強剛や振戦等の錐体外路症状、発汗や頻脈等の自律神経症状を主徴とし、放置すると死に至る重篤な副作用で、ほとんどが原因薬剤の投与後、減量後、中止後の1週間以内に発症する。特に抗精神病薬(急激な増量や頻回の筋肉内注射が危険因子)によるものが多いが、抗うつ薬、気分安定薬、パーキンソン病治療薬、抗認知症薬のほか、制吐薬等の精神神経用薬以外の薬物による事例も報告されている。発症機序と病態は十分に解明されていないが、黒質線条体や視床下部での急激で強力なドパミン受容体遮断、あるいはドパミン神経系と他のモノアミン神経系との協調の障害といったドパミン神経系仮説が支持されている。理由として、①原因薬剤の多くは共通して、ドパミン受容体遮断作用を有する、②ドパミン作働薬の中断が時に悪性症候群を惹起する、③ブロモクリプチン等のドパミン作働薬が悪性症候群に有効であることがある。その他、ドパミン/セロトニン神経系不均衡、ノルアドレナリン(ノルエピネフリン)やコリン系等の神経伝達系の関与、ドパミンD2・D3受容体遺伝子多型との関連、薬物代謝酵素CYP2D6遺伝子多型の欠失との関連も報告されている。