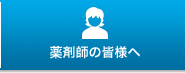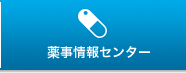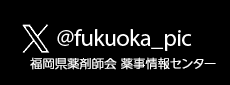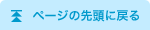質疑応答
質疑・応答をご覧になる方へ

福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。
回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。
県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。
質疑・応答検索
相談内容をクリックすると回答内容がご覧になれます。
※相談内容を検索する際に、検索語に英数字が含まれる場合は、半角と全角の両方での検索をお試しください。
| レボドパの吸収は、食事の影響を受けるか?(薬局)
相互作用 |
|
| 年月 | 2013年9月 |
レボドパは、小腸上部から長鎖中性アミノ酸(LNAAs)輸送系を介して吸収される。また、胃液pHが低いほどレボドパの可溶性が高まり、吸収率が向上する。食事により、胃液pHの上昇、胃排出時間の遅延、また蛋白質の加水分解によって生じるLNAAs(イソロイシン、ロイシン、フェニルアラニン等)が、レボドパの吸収と競合するため、レボドパの吸収遅延・減少が起こり、結果として運動応答開始時間の遅延と薬物治療効果の短縮が起こる。そのため、食前服用の方が薬物吸収、治療効果が良い。吸収率向上のため、胃酸pHを下げる酸性飲料やビタミンCとの同時服用や、ガスモチン(モサプリドクエン酸塩)等の胃内容物の排出を促進する薬剤の併用、日中の蛋白質摂取制限等も行われる。一方、レボドパ・脱炭酸酵素阻害薬配合剤では、急峻なレボドパの血中濃度上昇によるwearing off現象の回避のため、食後投与が推奨される。