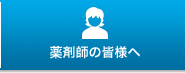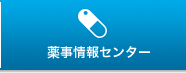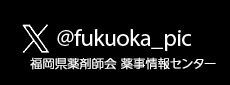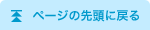質疑応答
質疑・応答をご覧になる方へ

福岡県薬会報に掲載している「情報センターに寄せられた質疑・応答の紹介」事例です。
回答はその時点での情報による回答であり、また紹介した事例が、すべての患者さんに当てはまるものではないことにご留意ください。
県民の皆様は、ご自身の薬について分からなくなったなどの場合には、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。相談しやすい“かかりつけ薬局”を持っておくのがよいでしょう。
質疑・応答検索
相談内容をクリックすると回答内容がご覧になれます。
※相談内容を検索する際に、検索語に英数字が含まれる場合は、半角と全角の両方での検索をお試しください。
| サナダムシの駆虫法は?(薬局)
疾病・治療法 |
|
| 年月 | 2024年10月 |
真田紐に似ていることから名付けられたサナダムシとして知られる条虫は、成虫が腸管に寄生し、魚を感染源とする条虫症の中でわが国で最も発生頻度が高いものは日本海裂頭条虫症である。幼虫が寄生したサケ・マスを、生食や加熱不十分な状態で摂取して感染する。その他、幼虫が寄生した牛肉や豚肉の生食や加熱不十分な状態で摂取し感染する無鉤条虫症(牛肉)や有鉤条虫症(豚肉)などがあるが、わが国ではほぼ輸入感染例である。
日本海裂頭条虫は、体長5~10mで頭部の方は糸のように細く、下へ行くほど幅が10~15mmほどにもなる大型の寄生虫であるが、組織への侵入性がなく、特異的な症状はなく軽微なことが多い。下痢、腹痛、腹部膨満感などの消化管症状がみられることがあるが、片節(成虫の体の一部)が肛門から排出されることによる不安感、不快感、恐怖感が主症状となる場合が多い。排便時に虫体体節の排出で気づくことが多い。
日本海裂頭条虫の駆虫法には以下の2つの方法があり、第一選択はプラジカンテル投与である。駆虫効果判定は、虫体の頭部が完全に排出されたかを確認する。治療1~2ヶ月後に便検査を再び行い、虫卵の陰性を確認する。
| 抗寄生虫薬を使用する駆虫法 | 水溶性消化管造影剤を使用する駆虫法 | |
|---|---|---|
| 治療方針 |
プラジカンテル(ビルトリシド600mg錠)を使用する(保険適応外)。 下剤を併用すると虫体回収が容易で、駆虫効果判定としての頭節有無確認が行いやすい。 |
アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン(ガストログラフイン経口・注腸用)を使用する(保険適応外)。 患者の苦痛が大きいことや放射線被曝の観点から、第一選択の治療法とはならない。 |
| 駆虫前日 | 低残渣食や大腸検査食あるいはそれに準じる食事とし、夜に下剤を投与。 (例)20時頃にクエン酸マグネシウム34g(マグコロール散68%分包50g 1包)を 150mLの水に溶かして服用し、さらに21時頃にセンノシド24mg(プルゼニド錠12mg2錠など)を500mLの水とともに服用する。 |
|
| 駆虫当日 | 朝食は中止する。 午前中にプラジカンテル10mg/kgを1回服用し(保険適応外)、その2時間後にクエン酸マグネシウム34g(マグコロール散68%分包50g1包)を300mLの水に溶かして服用する。 |
朝食は中止する。 十二指腸ゾンデを経鼻あるいは経口的に挿入し、十二指腸水平脚に留置する。次いでガストログラフイン300mLを注入する(保険適応外)。X線透視で観察すると、腸管腔内を虫体が下降していく様子が観察できる。虫体の下降がみられなければ、ガストログラフインを100mLずつ追加する。虫体の下降がみられない場合でも、総量500~600mL前後で止めておく(患者が気付かない状況下で、治療前に既に自然排虫した後の場合もあるので注意する)。虫体の下降がみられれば十二指腸ゾンデを抜去し、トイレで排便させると虫体が排出される。 |
(寄生虫症薬物治療の手引き-2020-改訂第10.2版より引用 一部改変)